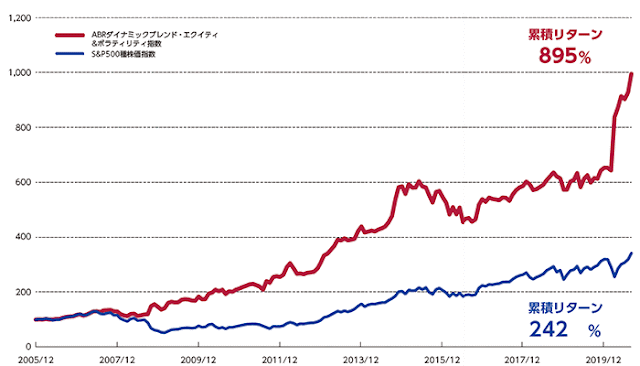2024年8月18日日曜日
日経平均VI先物から撤退します
2023年12月24日日曜日
2023年の振り返りと2024年の目標
2023年10月9日月曜日
投資からの撤退戦
手間いらず(2477)
iシェアーズ 米国債20年超(為替ヘッジ有)(2621)
タイミングをみて1000万円くらいまで買い増しして、2年以内に2200円くらいで売却出来たらいいなと思っています。VIXと違って、見込み違いでも大損することはないと思うので、深く考えていません。自分では手堅い投資をしていると思ってるんですが、どこかに落とし穴があるんでしょうか。大損したら、このブログを読み返したいと思います。
既にインフレは抑制されつつあって、FRBが景気後退しないように利下げを行うのは、ほぼ100%起きることだと勝手に思っています。利下げで株価が上がるか下がるかは、全く分かりませんが、米国債価格が上がるのは堅いので、米国債を買って、金利下落の恩恵を受けようという算段です。
こんなに上がるのが分かりやすい相場もなかなか無いと思うので、特定口座でも約200万円分買い増ししました。これで、合計約700万円分です。本当は700万円だけではなく、上がらないメタウォーター(9551)のような株も売却して、2,000万円くらいで勝負をかけたいんですが、「卵は一つのカゴに盛るな」の格言に反しているので、踏み切れません。どうしたものか。
日経平均VI先物
アメリカン ウォーター ワークス(AWK )
その他
2023年6月1日木曜日
どなたか祝日に日経平均VIを算出してください
1 日経平均VIは祝日に算出されていない
算出要領によると「大阪取引所の日経平均オプション取引の日中立会の時間帯に、15秒間隔で算出しています。」とあり、日経平均オプションは昨年の9月から始まった祝日取引の対象なので、祝日にも指数が算出されていないとおかしいです。日経インデックス事業室に問い合わせたところ、
>現在サイトに掲示している算出要領は、2021年12月に算出に用いる金利を変更した際に改定したもので、大変恐縮ですが祝日取引に関する事項は未記載です。
>近々当該事項を追記したものに差し替えさせていただきます。
私は日経平均VI先物の取引指標の1つに日経平均VI指数を使っているため、祝日にも算出してもらいたいんですが、よくよく算出式を見たら、祝日に算出できない理由がわかりました。
2 祝日に算出できない理由
日経平均VIの算出には、日経平均オプション価格と日経平均先物価格の他に「前営業日付のTORF(東京ターム物リスク・フリー・レート)1カ月物」の数値が使われています。この「TORF」とは、世界的な不正で公表が停止された「円LIBOR」の後継の金利指標で、東京営業日の17時に公表され、祝日は対象外です。だから日経平均VIの方も算出されないんですね。
3 誰か算出・公表してください
「前営業日付のTORF1カ月物」は直近の公表値でいい(どうせ月曜日は金曜日の値を使用する)ので、祝日取引時間中に日経平均オプション価格と日経平均先物価格から日経平均VIを算出・公表してくれないでしょうか。一度は自分で算出しょうと思いましたが、数学が苦手な私には荷が重すぎました。
日経平均オプション価格と日経平均先物価格は、auカブコム証券とIB証券のAPIで取得できます。
問題は「TORF1カ月物」をどう取得するかですが、QUICK APIsは利用料が超高そうなので、ここで確認できる24時間遅れの「TORF」はどうでしょうか。(スクレイピングできるかは未確認)
本家のように15秒に1回は無理でも15分に1回くらい公表されたら、世界の数十人には需要があると思います。なんなら始値と終値だけでもいいです。どなたか公表を始めたら教えて下さい。
2023年5月14日日曜日
ChatGPT に日経平均VI先物の自動売買プログラムを書いてもらった[kabuステーションAPI]
●ChatGPT のアカウント作成
●頼み方
●注意点
●最後に
2023年3月19日日曜日
米国債ETFを400万円分購入
●個別株
●日経平均VI先物の自動売買
2023年2月20日月曜日
130万円分の米ドル建MMFを購入
米ドル建MMFを購入
auカブコム証券に口座開設
日経平均VI先物の自動売買に挫折
2022年12月24日土曜日
VIXショート出来ないなら日経平均VI先物を売ればいいじゃない
インタラクティブ・ブローカーズ証券
SBI証券
auカブコム証券
岡三オンライン証券
フィリップス証券
光世証券
2022年4月1日金曜日
VIXショートできる証券会社6社を比較
【GMOクリック証券】
【インタラクティブ・ブローカーズ証券(IB証券)】
【IG証券】
【サクソバンク証券】
【LINE証券(LINE CFD)】
【インヴァスト証券】
【その他国内証券会社】
【海外FX会社】
◎参考
2022年2月28日月曜日
現在のポートフォリオ
2021年11月4日木曜日
VIX先物の始値・高値・安値のデータ集め
2021年3月29日月曜日
「米国株式ボラティリティ戦略(旧:米国株式ボラティリティ戦略ファンド)」は買いか
面白い投資信託を見つけました。
今まではVIX関連の投資信託といえばVIX先物・ETN等をアクティブ運用する「楽天ボラティリティ・ファンド」(純資産約8億円)しかありませんでしたが、2020年10月29日に「米国株式ボラティリティ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」という投資信託が設定されていました。(現名称:PayPay投信 米国株式ボラティリティ戦略(為替ヘッジなし))
「米国株式ボラティリティ戦略ファンド」の仕組みはざっくり次のとおりです。
○ S&P500先物の買建て、VIX先物の買建て、キャッシュ(米国の短期国債等を含む)の3資産に機動的かつ適正な配分を行なう。
○ 資産配分比率はABRダイナミックブレンド・エクイティ&ボラティリティ指数(ABR指数)が活用するクオンツモデルで決定する。(モデルの詳細は不明。S&P500+現金は最大比率100%、VIXは50%)
○ ABR指数は、株価指数の変動率(ボラティリティ)のモメンタム(勢い)を計測し、そのトレンドをフォローするクオンツモデル
要するに、基本的にS&P500先物とVIX先物のロングをしていて、その比率を変えることで、平常時には、S&P500先物上昇の恩恵を受け、市場混乱時には、VIX先物上昇の恩恵を受けようという思想です。
こういう指数を自分で作ってみたいですよね。
S&P500+VIXロング+VIXショート+キャッシュのうち1~2つの組み合わせで、シグナルが来たら比率を変えるとか。バックテストどおりに売買できないですが。
コロナショックで指数が上手くいったので、商品化した匂いがします。
「楽天ボラティリティ・ファンド」は長期投資のヘッジ用の商品という売り方ですが、「米国株式ボラティリティ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」はこれ一本で済むように設計されているようです。
最初は面白そうだと思いましたが、現状では、買うつもりはありません。
理由は、
○ VIX先物をロングする期間が長いとコンタンゴで損する。上のチャートでも2014年~2016年のS&P500指数が横ばいのときに、コンタンゴで大きくやられている。
○ VIX先物のショートをしないので、美味しいところが取れない。
○ 実質信託報酬:1.855 %という高さ
○ 純資産約2億円という過疎っぷり
やはり、VIX先物をロングし続けるというのは、保険料としては高すぎると思います。
2月の月次レポートを見ても、S&P500指数:VIX先物=95:5の比率ですが、S&P500指数が前月末比+2.76%となったのに対し、VIX先物は▲23.88%だったため、トータルリターンは+2.67%とS&P500指数に劣後しています。
誰か天才がVIXショートも組み合わせて、3年で2倍になる指数とそれに連動する投資信託を作ってくれないでしょうか。
2020年9月5日土曜日
米国VIブルETF(UVXY)を自動売買する方法(備忘録)
備忘録と言いつつ、実際には自動売買していないため、机上の空論ですが、やろうと思えば案外簡単に出来きそうだなと思ったので、一応書き留めておきます。
VIX関連の有価証券をプログラミング売買するには、IB証券に口座を開設して、月10ドル払って価格データを購入し、Pythonでプログラムを作って、AWSなどからAPIでIB証券に発注するのが唯一の正解だと思いますが、相当ハードルが高いです。
そこで、ノンプログラミングで出来る方法をざっくり考えてみました。
(ちなみに、たぶん自動売買はGMOクリック証券の規約に違反します。)
1.データの取得
GoogleスプレッドシートにVIX指数やVIX先物などのリアルタイムデータ(に近いもの)を表示します。データは、Investing.comなどからWebスクレイピングで取得します。IMPORTXML関数というのを使えば、プログラミング不要で非常に簡単にネット上の文字情報を引っ張って来れます。
売買シグナルにVIX先物の第2限月の価格データが必要な場合は、CBOEの公式サイトから価格情報(10分遅れ)を取得します。
ただIMPORTXML関数を組んだだけでは、価格情報が更新されません。
Googleスプレッドシートは1日6回まで自動更新する「トリガー機能」というのがあります。1時間単位でしか設定できないため、4:59などには設定出来ないので、終値付近で売買するのなら、シカゴの市場が閉まる2~3時間前にトリガーを設定します。
2.売買シグナルの作成
「6%以上先物プレミアムでシグナル点灯=新規売建。シグナル消灯=決済」などのルールを決め、EXCELと同じ要領でGoogleスプレッドシート上で「(前日終値ではシグナルが点灯していない AND 今日シグナルが点灯した)場合は、A1セルに"BUY"を表示」というような関数を組みます。3.証券会社への発注(PCの場合)
PCから売買する場合は、個人なら完全無料で使えるUiPathというRPA(自動化)ツールを使うのが楽です。UiPathは現時点で、無料で使えるRPAツールの中では、最良のソフトだと思います。UiPathで乃木坂の先着順のチケットを購入するBotを作ったことがありますが、操作は特に難しくはありません。マクロのように、画面上のクリックを再現する機能もあります。
UiPathを定時起動→ブラウザ起動し、URL指定でGoogleスプレッドシートを表示→A1セルを見る→”BUY”ならURL指定で証券会社のサイトを表示→ID & パスワードを入力してログイン→URL指定で米国VIブルETF(UVXY)の個別ページを開く→枚数を入力して成行で購入→建玉一覧ページからロスカットレート変更→終了
というような流れで、いくつか条件分岐させれば、作れると思います。
4.証券会社への発注(スマホの場合)
UiPathの代わりに、Androidなら「MacroDroid」というRPAアプリがあります。このアプリを利用してGoogleスプレッドシートを参照して、「CFDroid」を操作するマクロを組めば、売買可能だと思います。
もし、Googleスプレッドシートを直接参照しての条件分岐が難しければ、「Googleスプレッドシートから5分でアプリが作成できる」と言われる無料サービスの「Glide」でアプリを作って、そのアプリを参照する方法にすれば、上手くいくかもしれません。
-----------------------------------------
危ないですし、なんだか大損しそうですね。
手動で売買しているとメンタルが持たないので、自動売買を考えましたが、そもそも手動で勝てないシグナルでは、自動でも勝てません。
現状の売買シグナルには、まだ何らかのエッセンスが足りないと思うので、自動売買よりもそちらを真剣に考えたほうが良さそうです。
というより、こんなことを考えてる時間があったら、QQQ(米国NQ100)を買ったほうが儲かりますかね。
2020年6月21日日曜日
AWKから2度目の配当
AWKから配当
年末にNISAで購入してから累計80.33ドルの配当をもらいました。本来は、これを再投資しないと意味がないですが、80ドルで買える株があまりないので、放置してます。
VIXの分析
VIXの分析をして以来、「VIX先物と時差相関のあるデータを探す」ことが出来ないかと思い、多変量解析などの手法やPythonについて調べています。
Pythonならスマートにできるかと思いましたが、初心者には厳しそうです。
VIX先物価格と様々な経済指標などのCSVを取り込んだら、勝手に時差相関を見つけてくれる夢のような統計分析ソフトはないでしょうか。
VIX先物の第2限月のリアルタイムデータを得る方法
いちいち電卓で「VIX指数×1.06」を計算するのがめんどくさいので、ブログの右上にGoogleスプレッドシートを埋め込んでみました。
Webスクレピング(Webデータ抽出)の関数を入れて、毎朝1回、某サイトにコンスタント・マチュリティの終値データを取りに行っています。(1日1回なら許されるはず。)
金曜日にこのシグナルが出たので、ショートポジションを持ちました。しかし、土曜日の朝に確認したら、明らかに計算が間違っています。なので、第1限月と第2限月を拾ってきて、Googleスプレッドシートでコンスタント・マチュリティを計算する方式に変えました。
本当は先物のリアルタイム(実際には10分遅れ)データを
https://www.cboe.com/products/futures/vx-cboe-volatility-index-vix-futures
上のCBOEの公式サイトから持ってきて、Googleスプレッドシートでコンスタント・マチュリティを計算した結果を表示させようと思ったんですが、どうしてもWebスクレピングでデータを持ってこれません。(負荷対策でスクレイピング出来ないようにしている?)
VIX先物の第1限月のリアルタイム(に近い)データを見れるサイトはいくつかありますが、第2限月は、公式サイトとVIX Central くらいしか見つかりませんでした。VIX Central は、終値が調整後価格ではないので、参照したくありません。
しかし、コンスタント・マチュリティを計算するには、どうしても第2限月のデータが必要なので困っています。あとはIB証券と月10ドルで契約するくらいでしょうか。
ウィルスサイトを見つけた
VIX先物のリアルタイムデータを探している時に、検索結果の1ページ目にYahoo知恵袋風のロシアのウイルスサイトが出てきました。引っかかる人はいないでしょうが、お気をつけください。
2020年6月7日日曜日
VIX取引バックテスト結果 2020年版(第5回)
第1回はこちら。
前回記事はこちら。
※全編にわたり、正確性は保証できません。理解も記憶もあいまいです。
ここまでVIXショート戦略とVIXロング戦略を検討した結果、次のシグナルに基づき売買するのが最適だという結論に達しました。
●売りシグナル
コンスタント・マチュリティがVIX指数に比べて6%以上高くなったら米国VIブルETF(UVXY)売り。シグナルが点灯しなくなったら決済。
●売り例外
コンスタント・マチュリティが60以上の場合、シグナルが点灯していなくても米国VIブルETF(UVXY)売り。その後、シグナルの点滅があっても、30を下回るまで決済しない。その際、レバレッジは1倍とする。
●買いシグナル
VIX指数が米国VIに比べて2%以上高くなったら米国VI買い。シグナルが点灯しなくなったら決済。
●買い例外
コンスタント・マアチュリティが60以上になったら、シグナルが点灯していても決済。
しかし、まだ検討事項が残っています。
・売りと買い両方のシグナルが出ている時にどうするか。
・資金管理をどうするか。(レバレッジをどうするか。)
・税金を考慮したバックテスト結果
・電卓を叩かずにシグナルを確認する方法
売り買い両方のシグナルが出ている時
ショート戦略とロング戦略で見ている指標が異なるため、両方のシグナルが出ることがあります。
この時考えられるのは、
①両建て
②ショート優先
③ロング優先
④ノーポジ
の4つです。
資金的に2つのポジションを同時に建てるには、レバレッジ2倍以上が必要ですが、VIXショックの時は、レバレッジ1倍でもショートはロスカットにあっていたくらいなので、①両建ては計算していません。
また、ノーポジは機会を逃すので、計算しません。
「②ショート優先」と「③ロング優先」を確認したところ、意外にも成績がいいのは「③ロング優先」となりました。年間リターン(複利)は、「②ショート優先」90.3%に対して、「③ロング優先」165.6%でした。
「③ロング優先」の場合、1取引あたりの最大損失率は25%、約16年間で取引回数は583回、資産は約6,505,654倍、100万円が約6.5兆円になる計算です。有り得ないですね。
レバレッジは何倍まで掛けられたか
ここまでは、毎回資金の全額を投資する前提でしたが、現実的ではないので、多少のレバレッジを掛けて、残りを余力として持っておく戦略を考えてみます。
カジノのブラックジャック必勝法(カード・カウンティング)の賭け金の基本は、「賭け金は予想勝率が上がれば上げ、下がれば賭けから降りる。予想勝率に応じた最適な金額を賭ける。」ことらしいです。
この考え方がとてもしっくりくるので、VIX取引にも利用したいのですが、根本的に相場の世界で勝率をどう予想すればいいか分かりません。
Pythonで機械学習でもさせれば、勝率(期待値)を出してくれるんでしょうか。
とりあえず、取引1回あたりの最大損失率(-25%)は決済時点なので、終値と場中でどのくらい含み損を抱えるか、ざっくり計算してみました。
終値ベースでは含み損で最大-36%の時がありました。
場中はデータを持っていないので分かりませんが、過去1年間のUVXYの高値/終値を見ると、最大で38%高の日がありました。よって、場合によっては、場中に-50%以上の含み損を抱えることが考えられます。これだとレバレッジ2倍以上だと耐えられません。
終値ベースで10%や15%の含み損を抱えたら、損切りしたらどうかと思いましたが、下手に損切り(損失確定)させない方が、リターンがよさそうでした。
よって、いい手が思い浮かばないので、常にレバレッジ1倍で投資することにします。(実際には、例えば米国VIが15の時にロングした場合は、ロスカットレートを8にするなどして、現金は確保しておこうと思います。)
ちなみに、VIXショックの時は、売りシグナルが出ていなかったので、影響を受けませんでしたが、もし全力でショートポジションを持っていた場合、レバレッジ1倍でもロスカットにあっていました。
VIX取引にありがちな「コツコツドカン」ですが、こうならないためには、例えば100万円が300万円になったら、元金の100万円を抜いて200万円で取引するなどの自衛措置が必要かもしれません。
税金を考慮したバックテスト結果
上に記載の前提でバックテストを実施すると、年間利益(複利)165%、資金6,505,654倍になりました。
大雑把に毎年の年度末に利益が出ている場合は、利益から2割を引いて計算し直すと、年間利益(複利)138%、資金1,147,188倍に減りました。(損失の繰越は考えていない)
今年は大損しているので、問題ありませんが、もし今後利益を出せた場合、納税を先送りするために、CFDを両建てしてあえて損失を出す手法の実施を検討してもいいかも知れません。(取らぬ狸の皮算用)
手法の陳腐化
今まで、損益率ばかり見てきましたが、資金の推移をグラフで書くと、こうなります。始点は1です。
2017年頃から伸び悩んでいます。何が原因か分析できていません。
対数目盛では分かりにくいで、線形目盛にしましたが、2018年2月にピークをつけた資金が2020年2月のコロナショックで救われる直前までに35%まで減っています。最大ドローダウン率65%です。
ここまで、第1回から長々書いてきましたが、実際に取引していた場合、2017年以降の損失の積み重ねで、途中で確実にメンタルがやられて、取引を辞めていたと思います。
まとめ
5回に渡って長々と分析をしてきて、平均年利138%(複利)の方法を見つけましたが、2017年に風向きが変わって以降は、最大ドローダウン率が高く、リターンが低い状況が続いています。
2017年以降は、プレミアム率(ディスカウント率)を何%に調整しても、せいぜい30%程度のリターンしか得られないという結果になっています。これだと一発全損リスクに見合っていません。
ボロ儲けなのを知り、多くの投資家が同じ投資行動をした結果、リターンが下がったのでしょうか。
正直、リスクリターンが見合っていませんが、せっかくやる気が出てきたところなので、新たに使えるシグナルが見つかるまでは、2017年以降のデータで数値を調整した右のサイドバーに記載のシグナルを基準に少額で売買してみたいと思います。
2020年5月31日日曜日
VIX取引バックテスト結果 2020年版(第4回)
第1回はこちら。
前回記事はこちら。
※全編にわたり、正確性は保証できません。理解も記憶もあいまいです。
今回はVIXロング戦略の最適な取引ルールを検討したいと思います。
【追記:米国VIの理論値の計算を間違ってしまい、これ以降の全ての数値が違います。話半分で読んでください。(致命的なミスですが、記事を直す気力はありません。)】
結論から書くと、
●シグナル
VIX指数が米国VIに比べて2%以上高くなったら米国VIの買い。
●例外
コンスタント・マアチュリティが60以上になったら、シグナルが点灯していても決済。
としました。
※ここでの「コンスタント・マチュリティ」とは、VIX先物の第1限月と第2限月を合成したものをいいます。
バックテストでは、この条件だと年率67.3%(複利)となり、約16年間で1万ドルが約3,889万ドルになりました。
※実際にはバックテスト通りには取引できません。
疲れてきたので、ざっくり書きます。
米国VIの理論価格とNAV(基準価格)の算出
第1回で買建(ロング)は米国VIですることにしたので、まずは米国VIの理論価格を算出します。
米国VIは毎月第2水曜日に当月限から期先にロールオーバーする(乗り換える)ので、残存期間5日で乗り換えるということで試算しました。実際には祝日があると違いますが、気にしません。
米国VIの理論価格を算出した後は、2004年の先物取引開始日を1万として、ロールオーバーするとコンタンゴで減価(バックワーデーションで増価)する擬似的なNAVを算出しました。
最適なシグナルを確認
まずは、「VIX指数× n > 米国VI 」を見てみます。参照原資産が常に先物の第1限月というわけではないので、米国VIの価格そのものと比較しました。
青線が年間リターン(複利)で、オレンジ線が1取引の最大損失率です。
nが1%違うだけで、結果が大きくことなるため、ショートよりも繊細で難しい印象です。
次に、コンスタント・マチュリティです。
青線が年間リターン(複利)で、オレンジ線が1取引の最大損失率です。
ショートとは逆で、コンスタント・マチュリティを使用すると非常に悪い結果になりました。
ちなみに第1限月の先物価格でも比較しましたが、いい結果は得られませんでした。
一番リターンがよかった米国VIのn=1.02 のポジション保有日数は 1,373日でした。(長い気がする)
そして、VIXショート戦略で決めた取引ルールのポジション保有日数は 2,569日でした。
このうち、ポジションが重なる日(=ロングとショートを両建てする日)が合計 697日もありました。
シグナルが両方とも出た場合は、ショートを優先したり、ノーポジにするなど最適な方法を次回検討します。
損失を減らすには
とりあえず、一番リターンがよかった米国VIのn=1.02 の時の損益率の散布図を見てみます。
まず、横軸に新規買建した時点の米国VIをとりました。
損失を出したポジションとの相関は見られません。
次に横軸に新規買建した時点のコンスタント・マチュリティを取りました。損失を出したポジションとの相関は見られません。
最後にコンタンゴ率で見てみます。
線に傾きが生まれ、相関が見られますが、コンタンゴ率がマイナス(=バックワーデーション)のときも大きく利益が出ているので、下手なことをしない方がトータルで利益が増えます。
一応、米国VIのn=0.91 近辺も安定して利益が出ているため、その損益率の散布図も見てみましたが、特に相関は見つけられませんでした。
このままだと結構な頻度で大損するため、メンタル的に継続的な取引は困難だと思います。
利益を増やすには
利益を増やすためには、○○ショック時に頂上付近で手放すことが必要です。
まず、リーマンショック時は資産を3.8倍に増やしていますが、だいぶ峠を超えてから決済しているので、頂上で決済したいところです。
ショート戦略との整合を取るためにも、コンスタント・マチュリティが60以上になったら手仕舞いという例外規定を作ります。
この場合、資産は3.8倍で変わりませんでした。約2ヶ月の長期ポジションで、強いバックワーデーションの追い風があったので、頂上付近で利確しなくても、大きな利益が出せていました。
VIXショックでは、資産を1.4倍に増やしています。
コロナショックでは、資産を2.7倍に増やしているものの、2020/2/21からのポジションを2020/4/17の最終日も保有し続けているので、適切な戦略とは言えません。
これも、コンスタント・マチュリティが60を超えたら手仕舞いという例外規定を適用した場合、資産を5.2倍に増やせました。
まとめ
●シグナル
・VIX指数が米国VIに比べて2%以上高くなったら米国VIの買い。
●例外
・コンスタント・マアチュリティが60以上になったら決済。
第5回へ続く
(朝令暮改タイプなので、取引ルールを決めても、決めた通りに取引できない可能性が高いです。)
2020年5月24日日曜日
VIX取引バックテスト結果 2020年版(第3回)
第1回はこちら。
前回記事はこちら。
※全編にわたり、正確性は保証できません。理解も記憶もあいまいです。
今回はVIXショート戦略の最適な取引ルールの例外を検討したいと思います。
結論から書くと、
●例外
コンスタント・マチュリティが60以上の場合、シグナルが点灯していなくても米国VIブルETF(UVXY)売り。その後、シグナルの点滅があっても、30を下回るまで決済しない。その際、レバレッジは1倍とする。
となりました。
バックテストでは、この条件を加えると、年率67.7%(複利)となり、約16年間で1万ドルが約4,042万ドルになりました。
※実際にはUVXYは売禁になることが多いので、バックテスト通りにはいきません。
利益を増やすには
(今回のコロナショックで自分が出来なかったことですが、)○○ショックで上値が限られる場面では、シグナルが出ていなくても新規売建すべきだと思います。
まず、過去のコンスタント・マチュリティの推移を見てみます。
強制的な新規売建の基準を35あたりの中途半端な値にすると、コロナショックやリーマンショックでやられるため、60で試算してみました。当初は50にしようかと思いましたが、(たった2回の実績ですが、)50を超える時は必ず60も超えているため、60にしました。もっと細かく65にしようかとも思いましたが、実績が2度のみのため、過去の実績に細かく合わせると、オーバーフィッテイングになりそうですし、建値60は十分素晴らしいポジションなので、60にします。
例外規定を儲けない場合、リーマンショック期間(便宜的にコンスタント・マチュリティが終値で30を超えてから30を下回るまでの約8ヶ月間半とした。2008/9/29から2009/6/12)のリターンは、26%でした。
この期間に、「コンスタント・マチュリティが60以上になったら、新規売建し、その後、30を下回るまで決済しない。(レバレッジ1倍)」という条件で取引すると、65%のリターンでした。ロスカットにも余裕を持って対応できています。
ちなみに、VIX指数ベースで取引すると全損でした。あくまで取引しているのは先物なので、指数をみて売買するとUVXYが上がる前にポジションを持ってしまい、その後の暴騰で痛い目を見ます。(戒め)
一応、20まで決済しないパターンも計算しましたが、30あたりが一番よさそうでした。
ロングは3倍にだってなりますが、ショートは利益率99.9...%が限界なので、ある程度で決済してポジションを取り直したほうがリターンがいいようです。
ロスカットレートはざっくり計算すると、レバレッジ1倍で、コンスタント・マチュリティ 100相当まで耐えられるので、十分だと思います。
コロナショックで同様に計算すると、通常のシグナルは1度も出なかったため、リターン0%でした。
例外規定を実施した場合は、リターン50%でした。(2020/4/17に強制決済)
まだ他にも、通常時の決済の基準も改良の余地があるかもしれませんが、これが非常に難しいです。
損失はもっと早く切り、利益はもっと伸ばしたいので、シンプルでいい手法があれば、是非教えて下さい。
レバレッジは何倍まで掛けられたか
ロング戦略と一緒に考えてみます。
懸念
2018年2月5日のVIXショック時は105.92%、2月8日は-9.29%を記録しました。最近の乖離率は低いものの、相当の余裕を持ってロスカットレートを設定していないと、いつか寝首を掻かれる気がします。
まとめ
●シグナル
コンスタント・マチュリティがVIX指数に比べて6%以上高くなったら米国VIブルETF(UVXY)売り。
●例外
・コンスタント・マチュリティが60以上の場合、シグナルが点灯していなくても米国VIブルETF(UVXY)売り。その後、シグナルの点滅があっても、30を下回るまで決済しない。その際、レバレッジは1倍とする。
第4回へ続く
2020年5月17日日曜日
VIX取引バックテスト結果 2020年版(第2回)
前回記事はこちら。
※全編にわたり、正確性は保証できません。理解も記憶もあいまいです。
今回はVIXショート戦略の最適な取引ルールのシグナルを検討したいと思います。
結論から書くと、
●シグナル
コンスタント・マチュリティがVIX指数に比べて6%以上高くなったら米国VIブルETF(UVXY)売り。
となりました。
※「VIX」に「指数」という意味が含まれていますが、先物との違いを明確にするため、ここでは「VIX指数」と書きます。
※ここでの「コンスタント・マチュリティ(CM)」とは、VIX先物の第1限月と第2限月を合成したものをいいます。
バックテストの前提
・使用するデータは第1回で作成したUVXYの理論値
・10,000ドルからスタート
・最終日にポジションがある場合は強制決済して損益確定する。
・常に資金の全額を投資する。(とりあえず)
・とりあえずレバレッジは1倍とする。含み損は考慮しない。
・シグナル確認は終値ベースとし、シグナルを確認した当日終値でUVXYを新規売建し、シグナルがなくなった当日終値で決済する。(実現困難ですが)
・税金や手数料等はとりあえず考えない。
適切なシグナルを確認
いわいる「先物プレミアム」が何%の時が最も利回りが良かったのか検証してみます。
基本的に損益がプラスになるのは、0.87≦n≦1.2 です。
n≦0.96 あたりから、1取引あたりの最大損失率が50%を超えるので0.96からグラフにしました。
1番パフォーマンスがいいのは、n=0.97 のときで、16年間で投資資金が約697倍になりました。ただし、1%違うだけで、1取引あたりの最大損失率が50%を超えるため、非常にリスクが高いです。
n≦0.80の場合、2008年のリーマンショックやコロナショック時に早くにポジションを持ってしまい、資金がマイナスになります。
ただし、n≦0.65あたりになると、2004年の初日にショートしてからほぼ決済しなくなり、取引回数が16年間で1~2回になるため、資産が約2~4倍になります。それ以上極端な数字では、ポジションを持たなくなります。
思ったほど、リスク・リターンがよくありません。最大で年利50%近くありますが、1取引あたりの最大損失率があまりにも高すぎて、精神的に耐え難いので、再現が難しい気がします。
次に「VIX指数×n < コンスタント・マチュリティ」で同様に見てみます。
青線が年間リターン(複利)で、緑線が1取引の最大損失率です。
劇的にリスク・リターンが改善しました。
先物(第1限月)に比べて、取引回数が3割ほど減り、保有日数が5割ほど増えました。リスク・リターンが改善したのは、値動きが落ち着いているので、無駄撃ちが減ったためと思われます。
損益額を見るとこうなります。
あくまで過去の実績ですが、一番成績がいいのはn=1.06 のときで、投資資金が16年間で約2,000倍になりました。5%プレミアムよりも、6~9%プレミアムでショートする方がいいと言えそうです。
ここからは、n=1.06 を前提とします。損益率の散布図を見てみます。
2007年あたりから、結構な回数マイナス20%以上の損切りを強いられています。
実際に取引していたら、心が折れて、取引を辞めていたことでしょう。
また、細かく見ていくと、もったいない取引があります。例えば、コロナショックの3月に1度も取引していません。
他にも、1取引あたりの最大損失率を記録した2013年2月は、VIX指数が14.17の日にショートを開始し、翌日の18.99になった日に決済して約25%損失を出しています。この25%は金額にして約7千万円です。とても耐えられません。
少し改良の必要があります。
損失を減らすには
まず、下値が限られているのに20以下で新規売建するのは、個人的に非常に抵抗感があるため、「コンスタント・マチュリティ(CM)が20以下では新規売建しない」という条件の追加が妥当かどうか見てみます。
縦軸が損益率で、横軸がポジションを建てた際のCMです。
大半の取引は、CM20以下で建てるため、20以下で新規売建をしないと、リターンが非常に悪くなります。また、15以下でも利益率がいい取引がたくさんあるため、下手に制限を加えないほうがよさそうです。
この散布図を見て気づきましたが、せっかく建値40以上の最高のポジションを持っていても、ほとんど利益が出せていません。ここは改善の余地があります。(次回検証)
1取引あたりの最大損失率を10%程度まで下げたいのですが、どうしたらいいか思い浮かびません。他に新規売建した日のコンタンゴ率で見てみましたが、相関は見られませんでした。
ただ耐えるしかないのか...
何かの指標との相関を見つけたら是非教えて下さい。
このままだと、たぶん心が折られます。
第3回へ続く
2020年5月10日日曜日
VIX取引バックテスト結果 2020年版(第1回)
今までVIX(ボラティリティ)ショート戦略で概算で約600万円損しています。(たぶん)
この高い授業料から何かを学ばなければと思い、あれこれ検討してみました。やたらと長文です。
VIX関連商品を取引する日本人投資家にとってバイブル的存在?のVIX解説サイトroom5110を以前読みましたが、いくつか気になっていた点があります。これらを解決して、自分で納得できる取引ルールを作成したいと思います。
理想は、「○%先物プレミアムになったらレバレッジ○倍でUVXY売り、○%先物ディスカウントになったらレバレッジ○倍で米国VI買い」というシンプルな取引ルールを確立し、何があっても実行していくことです。
ちなみに、結論から書きたかったのですが、このブログを書きながらエクセルをいじっている段階なので、まだ結論が自分でも解っていません。
※全編にわたり、正確性は保証できません。理解も記憶もあいまいです。
気になっていた点
①room5110は、2017年11月で更新が止まっているので、2018年2月のVIXショックも、2020年3月のコロナショックもバックテストに含まれていない。そもそもバックテストで使用しているETFは2018年2月のVIXショックで早期償還されており、同じようなポジションを持ちにくい。
②
このバックテスト記事の結果、「0%先物プレミアムでボラティリティ売り、5%先物ディスカウントでボラティリティ買い」が最も全期間パフォーマンスが良かったが、「0%先物プレミアムでボラティリティ売り」するのは、タイミングとして遅いのではないか。「5%先物ディスカウントでボラティリティ買い」というのも、4%や6%でなく5%が一番結果がいいのか?
③
先物プレミアム/ディスカウントの基準を「第1限月のVIX先物」としているが、「コンスタント・マチュリティ」とした方がいいのではないか。残存期間が20日以上ある先物と、残り1日の先物では値動きなどが違うのではないか。
④
バックテスト計算では、建値に終値(引け値)を採用しているが、GMOクリック証券では「引け注文」ができないので、毎朝朝5時に起きていないと再現できない。始値ではバックテストにどう影響があるのか?
▶ これについては、現時点で2004年からのETF理論値の始値データを入手できてないので、検討できません。また、今後手に入る見込みもありません。
⑤
バックテストでは常に全力投資の前提であり、精神的に困難なため、再現性に欠ける。何度かに分けたり、余力を持つべきでは?
⑥
管理人の方がXIVなどの米国ETFのオプションを取引されていたようで、GMOクリック証券のCFDで取引している私の取引手法と合わない。例えば、ロスカット値をどこに置くかというCFDで取引する場合に非常に重要なポイントが抜けている。「証拠金を多めに積んで、耐え忍ぶ戦略は失敗する」という教訓を既に得ているので、どこかで適切に損切りしたい。
⑦
IB証券に口座開設する気はないが、GMOクリック証券のCFDの場合、新規売規制が頻繁に入るので、ポジションを建てられない場合はバックテスト通りにならない。ただしIB証券でも同様に規制が入るらしいのでしょうがないか?
ちなみに、2019年半ばまでのGMOの規制をまとめていらっしゃる方はいました。(ブログ) GMOの規制の網羅的なデータは問い合わせれば貰える可能性はあるのでしょうか。
⑧
税金2割を考慮するとバックテスト結果はどの程度変わるのか。
バックテスト用のデータ入手
そこのデータは、VIX先物取引がスタートした2004年3月26日からの第1・2限月先物価格・VIX・各種ETF理論価格等の終値価格が日別に入っています。(株式併合は調整済み)
私がダウンロードした時点で2020/04/17までのデータが入っていました。それ以降も手入力すれば作れますが、めんどくさいので、そのデータで計算しました。また、キレイに調整されたデータが同サイトで販売されていますが、ケチなので自分でいじりました。
投資対象
ただし、ロング(買建)は、他の2つのETFに比べ、取引時間が長いので逃げやすく、先物に連動しているため早期償還のリスクがないメリットがあるため、米国VIを使おうと思います。
SVXY(米国VIベアETF。S&P500 VIX短期先物インデックス(S&P 500 Short-Term VIX futures TR Index)の-0.5倍に連動)は動きが悪いですし、可能性は低いものの、これの買建は早期償還リスクがあります。これを取引したのでは、VIXショックで150万円損した際の教訓が無駄になるため、UVXY(米国VIブルETF。VIX short-term futures index × 1.5)をベースに考えます。(UVXYの売建なら早期償還もマイナスに作用しないはず...)
UVXYは構造的にコンタンゴで減価しやすく、またレバレッジでも減価しやすいというメリットがあります。なお、少額ですが金利が毎日掛かります。
UVXYは、2011年の設定時は倍率が2倍でしたが、VIXショックの影響で、2018年2月28日から1.5倍に変更されています。上でダウンロードしたエクセルでは、2018年2月27日までは2倍の理論値が入っているので、自分で1.5倍に直しました。
ただ、この計算だと、もともと入力されていた2018年2月28日以降のUVXY理論値と数%ずれます。他の計算方法が分かれば教えて下さい。
コンスタント・マチュリティ(CM)の自作
③の疑問点を解決するため、第1・2限月のCMの過去データを「VIX Constant Marurity Historical Date」などと検索しましたが、全然引っかからないので、しょうがないので自作しました。たぶん計算は合ってると思います。
ただ、これだとCMの終値しか分からないので、④の終値以外だとどうなってたかのバックテストが出来ません。データを見つけた方は教えて下さい。
第2回へ続く
2020年4月26日日曜日
600万円以上失ったコロナショックのVIX取引を振り返る
●最近の取引
VIXショートで500万円以上の損を出してからは、原油のショートを何度か仕掛けましたが、方向性は合っていたものの、ボラティリティが高すぎて、ことごとくロスカットにあいました。
原油はもう二度と取引しない所存です。(戒め)
●VIXショート
2番底を待っていますが、中々来ないので、とりあえず1月以降のVIXに関する取引をまとめます。
下手くその極みのような取引です。
ちなみに、これを作るために、今年になって始めて精算表を見たところ、年初来実現損益がマイナス600万円超えでした。我ながらビックリです。
赤矢印が新規買建(ロング)、青矢印が新規売建(ショート)、黒矢印が決済です。
まずは米国VIです。コロナショックすぐに規制が掛かり、ショート出来なくなったため、結果的に1月~2月合計で10万円程度しか損していません。
最後にロングした翌日に全決済してしまったため、本格的な上昇局面では、ノーポジでした。まさか80ドルまで上がるとは...
それにしても同日中の決済がこんなにも多かったとは気づきませんでした。方向性は合っていたので、証拠金を積んで耐えてれば、儲けられたのですが、実際には難しかったです。
短期投資の才能は全く無いとはっきり解ったため、もう二度と短期目的で新規にポジションを建てません。(戒め)
次に米国VIブルETF(UVXY)です。米国VIに規制がかかり、新規でショート出来なくなったために取引を開始しました。馬鹿の一つ覚えのように、ほぼショートしかしていなかったため、トータルで約600万円を失う結果になりました。
ちなみに最初に利益を出せたのは3/31の決済なので、それまでの黒矢印は全て損切りとロスカットです。
教科書に載せてほしいくらいの下手な取引ですね。(見にくい...)
教訓は、ポジションを何分割かに分けて建てるべきだったのに、1度に建ててしまったこと等々...たくさんあります。
●今後のVIX投資の方向性
あるブログで、「 誰も言う人はいませんが、結局VIX先物売り、或いはVIXインバースは先物の限月間の価格差を利用したサヤすべり取りを行っているわけです。」とあり、初心に返りました。
さらに、こちらのブログ(サヤすべり取りが流行らない理由)に「サヤすべり取りのお決まりの破滅パターン」が書かれていて、自分がまさにそうなっていると自覚しました。
これらを踏まえ、メインを株に戻します。
今保有している株式4銘柄は全て含み益です。株は長期投資のつもりで投資していて、結果論ですが銘柄選定も悪くないようです。たぶん株取引で損切りしたこともないと思います。よって、VIXよりもリスクリターンが圧倒的にいいです。
今はアマゾンやメタウォーターなどが気になりますが、個別株は買える水準の銘柄がないため、VOO(S&P500)、VGT(バンガード 情報技術ETF)かTECL(テクノロジー3倍)の購入を考えています。
ただ、実体経済が明らかに悪いのに、金融緩和だけで株価が上がりすぎているのではないかと思い、今はETFでも買いづらいです。
下が過去5年のチャートです。オレンジがS&P500に連動するVOOです。
株でもレバ3倍ETFなどを使えば、十分にハイリターンを狙えるため、私にとってリスクがとても高いVIX先物のサヤすべり取りは、十分に安全率が取れた場合にだけ、新規ボジションを建てて、長期保有することにします。(戒め)
十分に安全率を取るには、低いところでのロングは、長期でのコンタントでの減価リスクが高いため、結局、絶対的に高い水準の VIXショートしかしません。
具体的には、検討中ですが、原資産となるVIX先物が50を超えてる場合にだけショートするというルールを立てようかと思います。それだと、チャンスは10年に1度かもしれませんが、忍耐力さえあれば、その1回の取引でも十分に年率6~8%程度のS&P500を超えられる気がします。
しかし、今ちょうど、久々に先物ディスカウントになり、まさに今が売り時のような気がして、うずうずしているので、ルールを守れるか怪しいです。

.gif)